譲渡所得とは?課税方法や計算式について
更新日 2024年7月10日
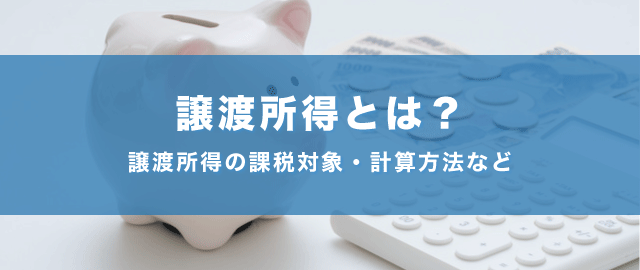
譲渡所得とは?
譲渡所得とは、一定の資産の売却などで生まれる所得のことを指します。たとえば株を売ることで得る利益は、この譲渡所得として扱われます。売買益が譲渡所得の対象になる資産には、以下のようなものがあります。
譲渡所得の課税対象になる資産の例
| 総合課税の対象 | 分離課税の対象 |
|---|---|
|
|
譲渡所得には「総合課税」の対象になるものと「分離課税」の対象になるものがあります。 総合課税とは、各所得を合算した金額に課税される方式です。分離課税とは、他の所得と合算せずに分離して課税される方式です。
課税対象にならない譲渡所得
資産の譲渡(売買や交換など)による所得でも、課税対象にならないものがあります。下記のような譲渡所得は非課税です。
課税対象にならない譲渡所得の例
- 生活用品の譲渡による所得
家具、家電、衣服など、生活に必要なものを譲渡したときの所得。 ただし、宝石や古美術品などの娯楽性が高いもので、30万円を超えるものの譲渡による所得は、課税の対象になる - 資産が競売などにかけられたことによる所得
破産や滞納により、住宅ローンなどの支払いができなくなった資産を、強制的に競売などで譲渡した場合の所得
たとえば、自宅で使っている扇風機は生活必需品といえます。これをネットオークションなどで売却しても、課税対象にはならないということです。 ただし、趣味で買った100万円のボートを売るような場合は、譲渡所得として課税されます。
譲渡でも他の所得に当てはまるもの
資産の譲渡によって生じる所得でも、下記のようなものは譲渡所得以外の所得として扱われます。
他の所得として課税されるものの例
- 商品や原材料などの棚卸資産を譲渡することによる所得 → 事業所得 or 雑所得
(棚卸資産とは、販売する目的で一時的に保有している商品・原材料などの総称) - 山林を伐採して譲渡した場合の所得 → 山林所得 or 事業所得 or 雑所得
たとえば、靴屋の個人事業主が商品のスニーカーを売ったら、その売上は事業所得に含めるということです。
譲渡所得の計算方法(総合課税)
土地や建物、株式などを売った場合を除いて、資産を売ったときの譲渡所得は総合課税の対象となります。 総合課税の譲渡所得は、ゴルフ会員権や美術品、宝石などの他、著作権や特許権などを譲渡した場合に生じる所得が当てはまります。
- 譲渡所得の計算式(総合課税の譲渡所得)
- 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用) − 50万円 = 譲渡所得の金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡価額 | 資産を譲渡する際の値打ち |
| 取得費 | その資産を買った時の購入費用。購入手数料や設備費、改良費なども含まれる。 使用期間により減価する資産の場合は、減価償却費に相当する額を控除した金額 |
| 譲渡費用 | その資産を売るために直接かかる費用 |
| 50万円 | 総合課税の譲渡所得に対する特別控除額(これを差し引いて譲渡所得がマイナスになることはない。つまり最高で50万円) |
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い
譲渡所得は、資産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けるのが原則です。「長期譲渡所得」のほうが、課税において有利です。
| 短期譲渡所得 (所有期間が5年以内) | 長期譲渡所得 (所有期間が5年超) |
|---|---|
| 譲渡所得の全額が課税対象 | 譲渡所得の1/2が課税対象 |
ここでいう所有期間とは、資産を取得してから譲渡するまでの期間です。資産を譲渡した年の1月1日時点で、所有期間を判定します。
譲渡所得の計算方法(分離課税:土地・建物)
土地や建物を売ったときの譲渡所得は「分離課税」の対象です。 他の所得とは合算せず、区別して税額を計算することになります。分離課税の対象になる譲渡所得の計算式は、以下の通りです。
- 譲渡所得の計算式(土地や建物の譲渡所得)
- 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除 = 譲渡所得の金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡価額 | 土地や建物を譲渡する際の値打ち |
| 取得費 | 土地や建物の購入費をはじめ、建築費用やリフォーム代、設備費などが含まれる。 購入代金や建築費の合計から、所有期間中の減価償却費に相当する金額は差し引く |
| 譲渡費用 | 譲渡する際に支払った販売手数料や収入印紙代など。 土地を売るために建物を取り壊したときの取り壊し費用や、建物の損失額などもこれに含まれる |
| 特別控除 | マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など、場合によっては特別控除が受けられる |
短期譲渡所得と長期譲渡所得
こちらも資産の所有期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます。 長期譲渡所得のほうが断然、税率が低くなります。
| 短期譲渡所得 (5年以内) | 長期譲渡所得 (5年超) | |
|---|---|---|
| 税率 | 所得税30% + 住民税9% = 合計39% | 所得税15% + 住民税5% = 合計20% |
平成25年から令和19年までは、復興特別所得税も
譲渡所得の計算方法(分離課税:株式)
株を売ったときの譲渡所得も「分離課税」の対象です。 他の所得とは合算せず、区別して税額を計算します。上場株を売った場合、シンプルに下記の税率で課税されます。
所得税 15% + 住民税 5% = 合計 20%
平成25年から令和19年までは、復興特別所得税も
なお、証券口座で「特定口座(源泉徴収あり)」を選んだ場合、上記の税率であらかじめ源泉徴収されます。 ですから、その譲渡益について確定申告をする必要はありません。
まとめ
譲渡所得は、一定の資産を譲渡することによって生じる所得です。 譲渡所得の課税方法は、総合課税か分離課税の2つに大別できます。
総合課税の譲渡所得には、ゴルフ会員権や古美術品、宝飾品などの他に、著作権などの知的財産権なども含まれます。 ただし、家具や衣服などの生活用動産の譲渡による所得は、譲渡所得として課税対象にはなりません。
申告分離課税の譲渡所得は、主に土地や建物などの不動産譲渡や、株式譲渡による所得が当てはまります。 土地や建物の譲渡については特別控除もあり、一定の要件を満たせばこれが適用されます。 また、保有年数によって税率が変わってくるので、譲渡する時期などを考慮すれば上手く税金をおさえることもできます。
