基礎控除とは?所得税48万円・住民税43万円の計算など
更新日 2024年9月09日
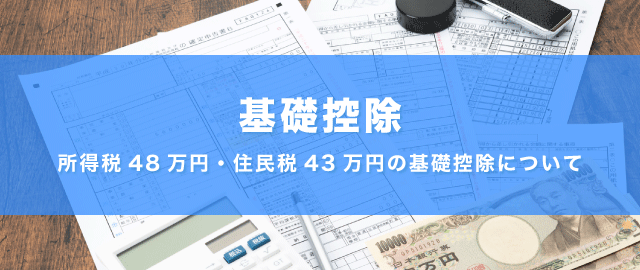
基礎控除とは?
基礎控除は、所得税や住民税の計算をするときに適用できる控除です。一部の高所得者をのぞき、多くの人が全額を控除できます。他の所得控除と違って、複雑な要件はありません。
「所得税の計算における基礎控除」と「住民税の計算における基礎控除」では、控除額が異なります。所得税における控除額は原則48万円、住民税における控除額は原則43万円です。これは個人事業主も給与所得者(会社員やアルバイトなど)も変わりません。
なお、基礎控除は改正によって控除額などが下記のように変わっています。改正前の制度と混同しないよう気をつけましょう
基礎控除の改正
| 所得税の基礎控除 | 住民税の基礎控除 |
|---|---|
|
|
| 2020年分(令和2年分)から適用 | 2021年度(令和3年度)から適用 |
所得税の計算 - 控除額は原則48万円
所得税の計算において、基礎控除の控除額は下記のとおりです。合計所得金額に応じて異なりますが、大半の人には「48万円」が適用されます。
基礎控除の控除額(所得税)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,500万円超 | 0円 |
| 2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 32万円 |
| 大半の人はここに当てはまる→ 2,400万円以下 | 48万円 |
個人事業主の所得税は、以下の計算式で算出します。下記の「各種控除」の部分に、基礎控除が含まれます。
- 所得税の計算式
- 収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
>> 個人事業主の所得税について
上述の通り、大半の人には48万円の基礎控除が適用されます。ですから「収入 − 必要経費」の金額が48万円以下の場合は、課税所得金額もゼロになり、所得税の納付が不要になります。
>> 所得48万円以下だと確定申告をする必要がない?
所得から差し引かれる控除の種類は、この他にもあります。例えば、病院でたくさん医療費を支払った人は「医療費控除」、子どもを養っている人は「扶養控除」など、個々の状況に応じた控除が用意されています。>> 個人事業主の所得控除一覧
ちなみに、個人事業主ではなく、会社に勤めている給与所得者の所得税は、以下の式で算出します。 会社員などの場合は「必要経費」が「給与所得控除」に置きかわるわけです。
- 給与にかかる所得税の計算式
- 収入 − 給与所得控除 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 控除額 = 所得税額
>> 給与所得者の所得税の計算方法について
なお「給与所得控除」の中に基礎控除が含まれるわけではありません。 赤文字の「各種控除」の方に、基礎控除が含まれます。
住民税の計算 - 控除額は原則43万円
まず、住民税の計算方法をおさらいしておきましょう。住民税は、みんな一律の金額を課税される「均等割」と、その人の所得に応じて金額がかわる「所得割」に分かれます。均等割と所得割の合計額が、納める住民税額です。
住民税の均等割
均等割の金額は、大体の地域で4,000円〜5,000円(1年あたり)です。基本的にはこの金額がみんな一律で課税されます。(地域によるが「合計所得金額が45万円以下」などの要件を満たせば非課税になる)
住民税の所得割
住民税の所得割は、以下の計算式で算出します。
- 所得割の計算式
- (所得金額 − 所得控除額)× 10% − 税額控除額 = 所得割の税額
上記の「所得控除額」の中に、基礎控除が含まれます。住民税における基礎控除の控除額は、以下のとおりです。
基礎控除の控除額(住民税)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,500万円超 | 0円 |
| 2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 29万円 |
| 大半の人はここに当てはまる→ 2,400万円以下 | 43万円 |
所得税計算での基礎控除額は「原則48万円」でしたが、住民税計算での基礎控除額は「原則43万円」です。
所得割の非課税限度額について
住民税には「非課税限度額」という考え方があります。所得割において、この金額は45万円です(同一生計配偶者か扶養親族がいない場合)。つまり、上の計算式の中の「所得金額」が45万円以下の場合は、住民税の所得割が課税されないわけです。
所得金額が45万円を超える場合、所得割は前述した式のとおりに計算します。所得金額から基礎控除を含む所得控除額を差し引き、所得割の税額を算出します。基礎控除の43万円と、この非課税限度額の45万円がごっちゃになったまま解説をしてしまっているウェブサイトも多いので注意しましょう。
>> 住民税の基礎控除額について
ちなみに、同一生計配偶者と扶養親族がいない場合は非課税限度額が「45万円」でしたが、 扶養親族等がいる方の場合は、非課税限度額が優遇されます。下記の式で非課税限度額を算出します。
- 非課税限度額の計算 - 扶養親族等がいる場合
- 35万円 × (扶養親族等の人数 + 1) + 10万円 + 32万円 = 非課税限度額
計算例:配偶者と子供を養っている場合
35万円 × (2 + 1) + 10万円 + 32万円 = 147万円
この場合は、非課税限度額が147万円ということです。
均等割と所得割の合計が、納付する住民税額
均等割と所得割を足したものが、納付する住民税の金額になります。
均等割(およそ4,000円〜5,000円) + 所得割 = 住民税額
>> 基礎控除と青色申告特別控除の改正について
>> 住民税の納付時期や計算方法
>> 所得控除の種類一覧へ
