現物給与とは?所得税が課税されるもの・非課税のものなど
更新日 2024年7月16日
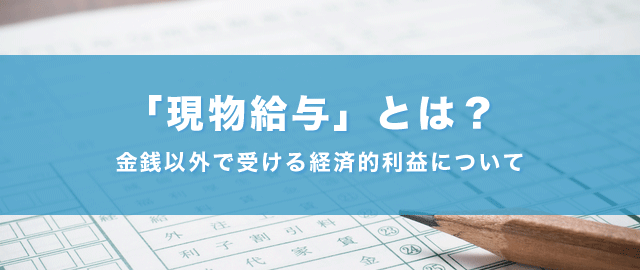
現物給与(げんぶつきゅうよ)とは?
現物給与とは、食事の現物支給や賃貸住宅の割安な利用など、金銭以外で受ける経済的利益のことを指します。 個人事業における必要経費のひとつ「給料賃金」はお金で支給するのが一般的ですが、その他の経済的利益も「現物給与」として、給与扱いになるということです。
例えば、社宅を安く借りたり、食事やユニフォーム・通勤定期券などを支給してもらうことによる経済的利益が「現物給与」です。 現物給与を支給した場合には、その現物を通貨に換算し、現物を受け取った従業員の給与所得の収入金額とします。
現物給与は、4つのケースに大別されます。
- 物品をあげたり、安く譲渡する場合
- 土地や家を無料で貸したり、安く貸す場合
- 福利厚生用施設の利用など、2以外のものを無料で提供するか安く提供する場合
- 個人的な債務を、免除か負担する場合
基本的には、現物給与にも所得税がかかります。従業員が、会社や個人事業主から現物給与をもらったら、それをお金に換算して、その従業員の収入(所得)として考える必要があるということです。 ただし後述のとおり、所得税が課されないものもあります。
現物給与の標準価額について
先述の通り、現物給与を従業員に与えた場合には、その現物を通貨に換算して、受け取った従業員の給与収入とします。 現物給与の中でもポピュラーな「食事」と「住宅」については、厚生労働大臣が都道府県ごとに、その価額を定めています。
>>全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
ちなみに、自社製品や通勤定期券などの現物給与については「時価」によって考えます。時価とは、その時点で売買した場合の価格のことです。
所得税が非課税とされている現物給与と手当
現物給与の中でも、所得税が課税されないものがあります。例えば、従業員が下記のものを支給してもらっても、所得税を課されません。
所得税が非課税の現物給与 - 主な具体例
- 通勤用の定期券(1ヶ月あたり15万円までのもの)
- 仕事に必要な制服、ユニフォーム
- 結婚祝い金、お見舞い金などで、常識的な金額
- 取得価額以上で、なおかつ、通常の販売価額の約70%以上の価額で値引販売する商品など
(いわゆる「社割」や「社販」のこと) - 通常の勤務時間外における残業、宿日直者に対して支給する食事
また、現物給与ではなく、手当として金銭で支給する下記のものも、所得税が課税されないことになっています。
所得税が非課税の手当
- 通勤手当のうち、一定金額以下のもの(電車通勤やバス通勤で、1ヶ月あたり15万円まで)
- 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
- 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
通勤手当として給料を加算されても、その増えた分に所得税はかからないということです。 ただし、社会保険料の算定基準には通勤手当も含まれるので、注意しましょう。 通勤手当が増えると、社会保険料の等級が上がって、納める社会保険料(厚生年金・健康保険)も増えることがあるということです。
>> 個人事業における「給料賃金」について
>> 個人事業における給与の仕訳方法について
>> 個人事業主が従業員へ給与を払うときの源泉徴収について
