退職所得とは?計算方法・課税方法など
更新日 2024年7月10日
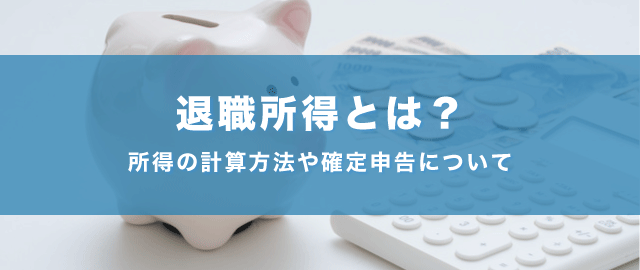
退職所得とは?
退職所得とは、勤務先からうけとる退職手当や、退職によって支払われる保険などの一時金による所得を指します。 俗にいう「退職金」は、この退職所得に該当します。下記のようなものが退職所得になります。
退職所得になるもの
- 退職により、勤務先から受け取る退職手当
- 退職により支払われる社会保険制度による一時金
- 退職年金契約に基づいて、生命保険会社や信託会社から受け取る退職一時金
- 解雇予告による手当や、退職者が弁済を受ける未払賃金
退職所得は、分離課税の対象です。基本的には、しかるべき税金があらかじめ差し引かれた金額が、退職金として会社から振り込まれます。 ですので基本的には、退職所得についてみずから確定申告をする必要はありません。
退職金は源泉徴収されて振り込まれますが、確定申告することも可能であり「申告分離課税」の対象に含まれています。 源泉分離課税の対象(確定申告できない所得)ではありません。後述のとおり、確定申告した方がいい場合もあります。
退職所得の受給に関する申告書
退職所得を受け取る際には、会社の指示にしたがって「退職所得の受給に関する申告書」に記入するのが一般的です。 これにもとづき、会社が源泉徴収して税金を納めてくれるので、納税者が退職所得について確定申告をする必要はありません。
- 「退職所得の受給に関する申告書」とは
- 支給されたものが、確かに「退職金」であると証明するための書類。 退職金は、通常の給与に比べると税務上で優遇されているので、このような書類を要する。
前述のとおり「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、会社で税金を計算し、しかるべき税金が差し引かれた金額が支給されるため、確定申告の必要はありません。
もし「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出しなかった場合には、退職金の収入金額から一律20.42%が源泉徴収されることになっています。この場合は、自分で確定申告をして税金の精算をしましょう。
退職所得の計算方法
退職所得は、以下の計算式で算出します。 なお、課税の対象になる退職所得の金額を「課税退職所得金額」と呼びます。
- 退職所得の計算方法
- (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得(課税退職所得金額)
収入金額
この場合の「収入金額」は、税引き前の額面です。(手取り額 + 税金 = 収入金額)
退職所得控除
退職所得控除は、勤続年数によって区分され、以下のように算出します。
| 勤続年数 20年以下 | 勤続年数 20年超 |
|---|---|
| 40万円 × 勤続年数 計算結果が80万円未満の場合は、80万円 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
勤続25年の場合には、800万円 + 70万円 × (25年 – 20年) = 1,150万円
この場合は、1,150万円が退職所得控除額です。
この人が退職金として1,500万円を支給された場合、退職所得は下記のとおり算出します。
(1,500万円 − 1,150万円)× 1/2 = 175万円(退職所得)
所得税の計算方法
先の例では、退職所得が175万円になりました。この場合で、源泉徴収される所得税額の計算をしてみましょう。 下表をみると「175万円」は、一番上の行に当てはまります。
令和2年分 所得税の税額表
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
源泉徴収される所得税 + 復興特別所得税
175万円 × 0.05 − 0円 = 87,500円(所得税額)
87,500 × 0.021 = 1,837円(復興特別所得税額)
87,500円 + 1,837円 = 89,337円(所得税額 + 復興特別所得税額)
2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税に加えて「復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)」をあわせて納付することになっています。 この復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を確保するための税金です。
確定申告した方がいい場合
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出した場合でも、確定申告をした方がいい場合があります。
年の途中で退職した場合
退職した年の所得が少ない場合や、退職後に再就職をしていない場合は、会社の年末調整が行われません。 この場合、確定申告をすることによって、すでに源泉徴収された税金が戻ってくる場合があります。
他の所得で赤字があった場合
退職後に事業を始めたり、不動産収入などがある場合、それらの所得に赤字が出れば、退職所得と「損益通算」ができます。 ただし、まずは不動産所得や事業所得の赤字を給与所得などで損益通算しなければなりません。 その上で赤字が残った場合に、最終的に退職所得との損益通算ができます。
退職所得のまとめ
退職金は本来「会社を定年まで勤め上げた人の退職後の生活資金」という意味合いのものです。 そのため、退職所得控除などの特例により、退職金にかかる税金を軽減する措置がとられています。
- 退職所得は分離課税の対象で、他の所得とは切り分けて考える
- 「退職所得の受給に関する申込書」を会社に提出する
- この申込書を会社へ提出すれば、しかるべき金額が源泉徴収されて振り込まれる
- 退職所得に関して、基本的に確定申告をする必要はない
- 退職所得を得た年について、確定申告した方がいい場合もある
会社を辞めたら、再就職しないかぎり基本的には年末調整されません。 その場合、あらかじめ源泉徴収によって納めすぎた税金があっても、精算されずに損をしてしまいます。
しかし、納税者が自ら確定申告をすれば、納めすぎた税金を返してもらうことができます。 会社を辞めた年の分は、自分で確定申告することを検討しましょう。
>> 会社員が確定申告で提出する書類
>> 会社員で確定申告が必要な場合・した方がいい場合
>> そもそも確定申告って何?確定申告の基本
>> 納めすぎた税金を返してもらうための「還付申告」
>> 個人事業を開業するまでの5ステップ
