雑損控除を受ける条件や計算方法などについて
更新日 2024年9月06日
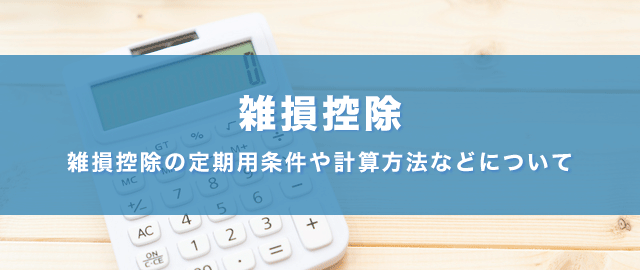
雑損控除とは、災害や盗難・横領によって資産に損害がでた場合に受けられる控除です。 「災害などで大変な目にあった人の税金を減らしてあげよう」という趣旨の所得控除です。
雑損控除の対象になる条件
雑損控除の対象は、損害の原因が以下のいずれかである場合に限られます。
- 震災や水害など、自然現象の異変による災害
- 火災や爆発など、人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
※ 詐欺や恐喝の場合は雑損控除の対象になりません
そして、以下のどちらにも当てはまる資産が、雑損控除の対象とされています。
- 納税者か、納税者と生計を一緒にする配偶者か親族が所有する資産であること
(納税者本人でない場合は、その年の総所得金額などが38万円以下の者) - 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること
(事業用の資産や貴金属などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらない)
雑損控除の計算方法
雑損控除として控除される金額の計算方法を見ていきましょう。まずは「差引損失額」を算出します。
- 差引損失額の計算式
- 損害金額 + 災害関連支出の金額 − 保険金などにより補てんされる金額
= 差引損失額
- 損害金額 = 損害を受ける直前の、その資産の時価を基にして計算した損害の額
- 災害関連支出の金額 = 災害により被害を受けた住宅や家財などを取り壊したりするために支出した金額など
- 保険金などにより補てんされる金額 = 災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金など
そして、次のいずれかで金額の多い方が、雑損控除として控除できます。
- 差引損失額 − (総所得金額等×10%) = 雑損控除額
- 災害関連支出の金額 − 5万円 = 雑損控除額
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) - 国税庁
災害減免法による所得税の軽減免除
災害による所得税の減免措置として「災害減免法による所得税の軽減免除(以下、災害減免)」という制度も用意されています。 この制度の対象になる人は「雑損控除」か「災害減免法による所得税の軽減免除」、どちらかを選択することができます。 両方を適用してもらうことはできません。
盗難や横領はこの対象にならず、損害の原因が「災害」に限られますが、所得が低い納税者にとっては「災害減免」を選択するほうが有利な場合が多いです。これを適用してもらうためには、以下の全ての条件に当てはまる必要があります。
- 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下
- 災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上
(損害金額 = 「保険金などにより補てんされる金額」を除いた額) - その災害による損失額について雑損控除を受けない場合
所得金額に応じて、軽減または免除される所得税の金額が変わります。
| 所得金額の合計額 | 軽減 or 免除される所得税の金額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 所得税額の全額が免除される |
| 500万円 〜 750万円 | 所得税額の50%が軽減される |
| 750万円 〜 1,000万円 | 所得税額の25%が軽減される |
「雑損控除」や「災害減免」を受けるには、確定申告書に必要事項を記入し、 災害関連支出の金額の領収を証明できる書類を提出する必要があります。
>> 所得控除の種類一覧へ
>> 生命保険料控除
>> 地震保険料控除
