固定資産税とは?申告先・納付時期・仕訳例など
更新日 2024年7月27日
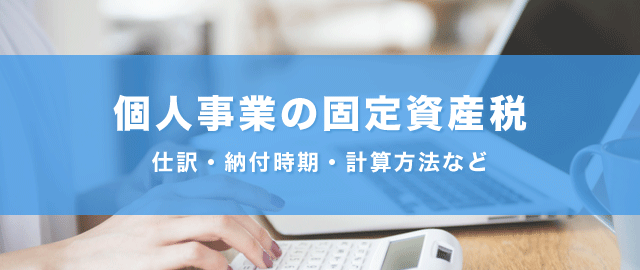
固定資産税とは?
- 固定資産税とは、固定資産の所有者に対して課せられる税金
- ここでいう固定資産を大別すると「土地・家屋・償却資産」
- 固定資産税は、自治体に納める地方税
- 自治体から届く納付書にしたがって納税する
- 自分で納税額を計算する必要はない
土地・家屋・償却資産の概要は、下表のとおりです。
| 土地 | 家屋(かおく) | 償却資産 | |
|---|---|---|---|
| 例 | 宅地・田畑・山林 | 家・店舗・工場 | 構築物・機械・工具 |
| 免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
| 対象者 | 個人・事業者 | 事業者のみ | |
| 申告 | 不要 | 必要 | |
| 税率 | 1.4% (地域によって異なる場合あり) | ||
事業者とは、個人事業主や法人のこと
固定資産税には「免税点」が定められています。 それぞれの免税点に満たなければ、固定資産税は課されません。
「償却資産」とは、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上の資産です。 たとえば、事業で使う「パソコン・デスク・看板・レジ・エアコン」などがこれにあたります。 これらの課税標準額の合計額が、150万円に満たない場合は、固定資産税は課されません。
なお、一般的な自動車には「自動車税」がかかるので、固定資産税の対象からは外れます。
固定資産税の計算式
固定資産の評価額を合計したものを「課税標準額」と呼びます。 この課税標準額に1.4%をかけて、固定資産税額を算出します。
固定資産税の計算式
評価額の合計 = 課税標準額(1,000円未満切り捨て)
課税標準額 × 税率 1.4% = 固定資産税額(100円未満切り捨て)
※ 地域によって異なる場合あり
固定資産税は自治体から郵送される納付書にしたがって納付するので、納税者がみずから固定資産税を計算する必要はありません。
固定資産の申告について
- 「償却資産」を保有する事業者(個人事業主・法人)が申告をする
- その年の1月1日時点で保有している償却資産を申告する
- 申告期限は原則1月31日
- 申告先は自治体(役所や都道府県税事務所)
- 「土地・家屋」は申告の必要なし(登記簿等で確認できるので)
先述のとおり、償却資産の免税点は150万円です。 保有している償却資産の合計金額がこの150万円に満たなくても、原則としては償却資産の申告をする必要があります。
固定資産税の納付時期
- 固定資産税は4回に分けて納めるのが基本(一括納付も可能)
- 地方税法では「4月・7月・12月・翌年2月」が原則
- ただし、これと異なる納付時期にしている自治体も多い
- 東京都23区は「6月・9月・12月・翌年2月」
その年最初の納付月である4月〜6月に、自治体から固定資産税の納付書が郵送されます。 納付時期が自治体によって異なるのと同様、通知書・納付書の郵送時期も地域によります。 この納付書にしたがって、4回に分けて納付すればOKです。一括で納付することも可能です。
固定資産税を納付したときの仕訳例
事業で扱うものの固定資産税であれば、「租税公課」の勘定科目で経費計上できます。 固定資産税を納付した場合、下記のように帳簿づけします。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年6月30日 | 租税公課 34,200 | 普通預金 34,200 | 音響機器の固定資産税 |
この仕訳は、固定資産税を事業用の銀行口座から振替納税したことを表します。 私用でも使うものについては、家事按分して一部を経費計上し、残りは事業主貸で仕訳しましょう。
>> 個人事業での償却方法まとめ
>> 個人事業主の税金納付時期まとめ
>> 個人事業主の主な節税方法まとめ
